

今回は、奈良時代末期に登場した初期荘園について、わかりやすく丁寧に解説していくね!
初期荘園とは
初期荘園とは、墾田永年私財法をきっかけに有力貴族・寺院たちが手に入れた広大な私有地(荘園)のことを言います。
墾田永年私財法ができるまで、日本の土地は全て朝廷の土地でした。
しかし、墾田永年私財法ができた後、有力者の私有地(荘園)がどんどん増えていきます。
荘園は姿形を変えながら、中世(室町時代)まで数百年もの間、日本に存続することになり、古代・中世の日本の政治・社会に大きな影響を与えました。
初期荘園は、そんな荘園が登場したてホヤホヤの頃の、プロトタイプ的な荘園なのです・・・!

ちなみに「初期荘園」って言葉は後世の学者たちが名付けた言葉であって、当時の人々が初期荘園と呼んでいたわけではありません。(念のために)
初期荘園ができた時代背景
繰り返しになりますが、初期荘園が登場した時代背景には、743年に制定された墾田永年私財法がありました。
当時の日本は、公地公民制という「日本では土地も民も全て天皇(朝廷)のもの!」っていう制度を採用していました。
そして朝廷は、その開墾した田地を民衆たちに分け与えて耕作させ、そこで収穫された稲の約3%を税金(租)として徴収していました。
※民衆たちに分け与えられた田地のことを口分田と呼びます。
・・・ところが、奈良時代に入ると、人々に分け与える口分田が不足するようになります。

うーん、口分田が足りなくなると、朝廷の税収も減って困るなぁ・・・。
そこで制定されたのが、墾田永年私財法でした。
墾田永年私財法は、「人々が自ら開墾した土地であれ、その土地の私有を永遠に認めますよ」っていう法律で、人々は自分の土地を手に入れるために積極的に開墾を行うようになります。

墾田永年私財法は、開墾した私有地からも租を徴収する仕組みだから、みんながたくさん開墾してくれれば、国の財政はひとまず安心だ。
こうして登場した公地公民制に縛られない新たな私有地のことを初期荘園と言います。
初期荘園を持てた人
墾田永年私財法によって初期荘園を得られたのは、貴族や寺院、地方の豪族など有力者に限られました。
開墾には多く農具や人手が必要だったので、広い土地を開墾できるのは、たくさんの人を動かせる権力・財力があるの人に限られたのです。
広大な土地を得られたのはもともと権力や富を持っていた人だけで、ほとんどの庶民たちは墾田永年私財法の恩恵を受けることができず、その結果、日本国内の貧富の差が大きく拡大しました。
話をまとめると・・・
初期荘園を持てたのは、貴族、寺院、地方豪族などのほんの一握りで、その少数の人たちだけが広大な土地をもつようになった・・・というのが初期荘園の実情でした。

初期荘園の実情は、なんだか資本主義における資本家と労働者の関係とよく似ているね・・・。
初期荘園の運営
初期荘園の運営は、その土地の物・人を荘園の持ち主(荘園領主)がすべて管理するのではなくて、各地の国司や郡司の協力を得ながら行われました。
墾田永年私財法の目的は税収を増やすことだったから、朝廷も有力者による開墾にも協力的だったのです。
開墾には、国司・郡司の協力により近隣農民たちが駆り出され、開墾地の拠点には荘所と呼ばれる事務所が設けられました。
初期荘園には荘園に住む住民(荘民)はいませんでした。
初期荘園は、あくまで国司・郡司によって動員された農民たちが耕作や収穫を手伝ってくれることで成り立っていたのです。
『荘園の中のものは全て荘園領主のもの!』という感じではなく、初期荘園は国司・郡司に依存しなければ存続できませんでした。
浮浪・逃亡
初期荘園は、重税に耐えきれなくなり口分田を捨てて浮浪・逃亡した人たちの受け皿にもなりました。

土地を開墾するには、多くの人手が必要だ。
私の命令に従って開墾の手伝いをしてくれるのなら、浮浪・逃亡した者もウェルカムで受け入れよう!

有力者の下でこき使われるのは嫌だけど、朝廷の重税に比べればまだマシだ。
急いで有力者のところへ逃げ込んで匿ってもらおう・・・。
平安時代に入ると、浮浪・逃亡する者が増え続けて荒廃した口分田が増える一方、初期荘園は浮浪・逃亡した人たちを吸収しながらじわりじわりと巨大化していきました。
初期荘園の衰退
浮浪・逃亡する者は増え続け、11世紀後半(1000年代後半)になると口分田は消滅し、日本の田地のほとんどが荘園となります。
浮浪・逃亡が増えたせいで、朝廷は戸籍による人民管理ができなくなり、「この人から税金(租・庸・調)を徴収する!」といった人に対する課税ができなくなりました。

これまで公地公民制をベースに税金を徴収していたけど、口分田が消滅して、戸籍もめちゃくちゃでどこに誰が住んでいるのかもわからなくなってしまった。
このままだと税金を徴収できなくなって、朝廷の財政が破綻してしまう・・・。
そこで朝廷は、土地や民の管理(公地公民制)を諦めて、広大に広がる荘園から税金を徴収することにしました。

なんかもう、土地や民を管理するのは無理だし、そこら辺にたくさんある荘園から税金を奪えば良くね?
この発想の転換によって、日本の税金の仕組みは、
「この人から税金を徴収する!」という人に対する税制
から
「この土地から税金を徴収する!」という土地に対する税制
へと変わっていきました。
しかし、荘園から税金を徴収しようとすると、当然、荘園領主の反発が想定されます。
そこで朝廷は、国司に強大な権限を与えて、荘園領主たちの反発に対抗しました。
こうして国司と荘園領主が対立するようになると、初期荘園は次第に衰退していきます。
繰り返しになりますが、初期荘園というのは、荒れた土地をどんどん開墾して作られた私有地のことです。
荒地を開墾して運営することは、口で言うほど簡単なものではなく、先ほどお話ししたように初期荘園は、荘園領主が自力で運営していたわけではなく、国司・郡司との協力関係で成り立っていました。
なので、国司と荘園領主が対立すると、初期荘園も存続できなくなっていった・・・というわけです
※ちなみに、国司の権限が強くなると、国司は郡司の仕事を奪うこととなり、郡司もまた衰退していきました。
国司と荘園領主が対立するようになると、荘園領主は荘園の経営に必要な人材を自前で調達しなければならなくなります。
そのため、荘園に住む人々は荘園領主の支配下に置かれるようになり、荘民と呼ばれるようになりました。
初期荘園から寄進地形荘園へ
初期荘園の衰退は、言い換えれば「荒地が新たに開墾されなくなった」ことを意味しています。
荘園領主たちは、開墾による荘園拡大よりも、利益や財産を国司に奪われないよう守りの姿勢に入るようになります。
荘園領主が国司から荘園を守る方法は大きく2つありました。
方法1:国司の支配を受け入れた上で、国司に賄賂を贈ったりして良好な関係を保つこと
方法2:武力や権力で徹底的に国司と争い方法
です。
方法①によって国司の支配下に置かれるようになった土地のことを公領と言います。
11世紀後半に入ると、日本の土地は、大きく公領と荘園のどちらかに属するようになり、公領と荘園で成り立つ土地制度のことを荘園公領制と言います。
方法②の場合、国司と争い方法の1つとして、荘園領主が自らの荘園の税金を免除するよう朝廷に圧力をかける方法がありました。
こうした圧力で税金が免除されることを不輸の権と言います。
さらに、不輸の権を持つ荘園が登場すると、不輸の権を得られなかった荘園領主たちには、こんなことを考え始める人が現れました。

いっそのこと荘園を不輸の権を持つ権力者に渡してしまって、荘園の管理権だけ認めてもらえれば良いんじゃね?
そしたら、荘園には不輸の権が適用されて税金から逃れることができるし、荘園の管理権さえ認めてもらえれば、私はこれまでと変わらず荘園運営ができる。
不輸の権を持つ人も、自分の荘園が増えるわけだから、断ることもあまりないだろうしな。
・・・あれ、もしかして私って天才じゃね!?
この裏技的な方法は、各地で行われるようになります。
不輸の権を持つ者に荘園がぞくぞくと寄進され、日本各地には、寄進された荘園で構成された広大な荘園が登場します。
こうした荘園のことを、「寄進された荘園で構成された荘園」ってことで日本史の専門用語で寄進地系荘園と呼んでいます。

荘園公領制の「荘園」も、初期荘園ではなく寄進地系荘園のことを指しているよ。
初期荘園が衰退すると、その代わりとして寄進地系荘園が荘園の主流となった・・・というわけです。
最後に、初期荘園と寄進地系荘園の違いを簡単にまとめておきます。
| 荘園の種類 | 成立方法 | 税金の徴収 | 荘園の住民 |
|---|---|---|---|
| 初期荘園 | 開墾して自ら土地を切り開く | 税金がかかる | 荘園領主との主従関係なし |
| 寄進地系荘園 | 他人から荘園の寄進を受ける | 税金がかからない | 荘園領主との主従関係あり |
確認問題
答:④墾田永年私財法
答:誤り
初期荘園は、自前の荘民を持たず、国司・郡司の協力に依存した荘園でした。
荘園と国司が激しく対立するのは、平安時代に入って公地公民制が崩壊した後になります。
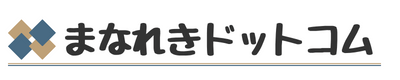

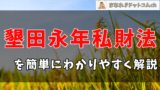


コメント