和を以て、貴しとなす
これは、多くの方が聞いたことがあるであろう、十七条憲法の最初の一文です。
この記事では、十七条憲法の全文を現代語訳付きで解説します。
十七条憲法は、1000年以上も前に作られたものです。
しかし、その内容は時代を経ても色せることなく、私たちが学ばなければならない教訓が多く含まれています

短い内容なので、その内容を一人でも多くの方に知ってもらえればと思います
youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎
十七条憲法が制定された経緯
まず初めに、十七条憲法がなぜ作られたのか、その時代背景を説明します。
十七条憲法は飛鳥時代の604年に制定されました。
ヤマト朝廷で働いている官僚たちが、仕事をする上で守るべき、17つの心得をまとめたものが十七条憲法です。
当時の日本は、豪族の協力体制で政治が行われていました。
朝廷で働く役人たちはざっくり言えば、今でいう派遣社員みたいなイメージでした。
役人たちは、朝廷から直接雇用されているわけではなく、豪族の命令で朝廷に派遣されていました。
そのため、役人にとっての従うべき上司は、朝廷というよりも豪族だったと言えるでしょう。
しかし、581年に隋という大国が登場したことで、この役人のあり方を改革する必要に迫られます。
日本は、隋に舐められないよう、豪族の協力体制ではなく、天皇が国の頂点に立ち、政治を執り行う体制へと生まれ変わろうとしていたのです。
そして、そのためには、朝廷で働く役人たちの意識改革が急務となりました。
問題は2点ありました。
1つ目は、先ほど紹介した派遣システムのせいで、役人の朝廷に対する忠誠心が薄いこと。
2つ目は、朝廷で働く役人たちの上下関係が、その役人たちの能力ではなく、派遣元の豪族のヒエラルキーによって決められていたことです。
役人たちが、出身豪族でマウントを取り合っていては、天皇のために、役人が一致団結することは不可能です
こうした問題を解決するために制定されたのが、十七条憲法です。
役人たちに対して、役人同士でいがみ合うことをやめ、協力して天皇のために仕事に励むことを求めたのです。
制定したのは聖徳太子と言われていますが、異論もあり、誰が制定したかははっきりとはわかっていません。
十七条憲法の全文解説
それではさっそく十七条憲法の本文を見ていくことにしましょう。
なお、原文は難しいので、私なりに現代語訳したものを紹介しています。
なるべく意味が変わらないよう、配慮したつもりですが、原文と齟齬がある場合もありますので、その点はご了承ください。
第1条
一にいはく、和
水上寺(http://www.suijoji.sakura.ne.jp/asia/kenpou17jou.html)以下同じ。
らかなるをもつて貴
しとなし、忤
ふることなきを宗
となす。人みな党
あり、また達
れるひと少なし。ここをもつてあるいは君
・父
に順
はず、また隣里
に違
へり。しかれども上和
らぎ下睦
びて、事を論
ふに諧
ふときは、すなはち事理
おのづからに通ふ、なにの事か成らざらん。
和を大切にし、反発しないことを基本とせよ。
人はみな、派閥を作りがちで、分別のある者は少ない。
そのため、君主や父に従わず、いきなり近隣との関係を壊すことがある。
しかし、上下がうまく調和して物事を議論すれば、
物事は自然と上手くいく。
成し遂げられないことなどないだろう。
第2条
二にいはく、篤
く三宝を敬
ふ。三宝とは仏・法・僧なり。すなはち四つの生れの終りの帰
、万
の国の極めの宗
なり。いつの世
、いづれの人か、この法
を貴
ばざらん。人はなはだ悪しきもの鮮
し、よく教ふるときはこれに従ふ。それ三宝に帰
りまつらずは、なにをもつてか枉
れるを直
さん。
仏、法典、僧の三宝を深く敬え。
三宝はあらゆる生き物の最後の帰依先であり、全ての国の究極の教えである。
どの時代のどんな人であっても、この教えを尊ばない者はいない。
人の中でもひどく悪い者は少ない。
よく教えれば従うものだ。
三宝に帰依しなければ、何をもって曲がったものを正すことができようか。
第3条
三にいはく、詔
を承
りてはかならず謹
め。君をばすなはち天
とす、臣
をばすなはち地
とす。天
は覆
ひ地は載せて、四つの時順
ひ行はれて、万
の気
、通ふことを得
。地
、天
を覆はんとするときは、すなはち壊
るることを致さまくのみ。ここをもつて、君のたまふときは臣
承
る、上
行ふときは下
靡
く。故
詔
を承りてはかならず慎め、謹
まずはおのづからに敗れなん。
天皇の命令を受けた時は必ず慎重に従え。
君主は天であり、臣下は地である。
天が覆い、地が支えるように、四季が順調に巡り、万物が調和して存在している。
もし地が天を覆そうとすれば、破滅を招くだけだ。
だから君主が命じたら臣下は従う。
上が行えば下は従う。
ゆえに命令を受けた時は必ず慎重にせよ。
慎重でなければ自滅することになる。
第4条
四にいはく、群卿
・百寮
、礼
びをもつて本
とせよ。それ民
を治むるの本、かならず礼びにあり。上
礼びなきときは下
斉
ほらず、下礼びなきときはもつてかならず罪あり。ここをもつて、群臣
礼びあるときは位
の次
乱れず、百姓
礼びあるときは国家
おのづからに治まる。
高官たちよ、礼節を基本とせよ。
民を治める基本は礼にある。
上に礼が無ければ下は整わず、下に礼が無ければ必ず罪となる。
君臣に礼があれば、身分の序列は乱れない。
民衆に礼があれば、国は自然と治まる。
第5条
五にいはく、餮
を絶ち欲
を棄
てて、あきらかに訴訟
を弁
めよ。それ百姓
の訟
へ、一日
に千
の事
あり。一日
すらもなほ爾
なり、いはんや歳を累
ねてをや。このごろ訟へを治むるひとども、利
を得て常とし、賄
を見ては
すを聴く。すなはち財
あるものの訟へは石をもつて水に投ぐるがごとし、乏
しきものの訴へは水をもつて石に投ぐるに似たり。ここをもつて貧しき民
はすなはちせんすべを知らず。臣
の道またここに闕
けぬ。
私欲を捨て、訴訟を公平に裁け。
民の訴訟は一日に千件もある。
1日でさえこれほどだ
まして年を重ねればなおさらである。
もし裁判官が利益を得ることを常とし、賄賂を見て判決を下せば、裕福な者の訴訟は石を水に投げるようなもので、貧しい者の訴訟は水を石に投げるようなものとなる。
そのため貧しい民は頼るべき所を知らなくなり、臣下としての道も欠けることになる。
第6条
六にいはく、悪
しきを懲
らし善
れを勧むるは、古
の良き典
なり。ここをもつて人の善れを匿
すことなかれ、悪しきを見てはかならず匡
せ。それ諂
ひ詐
くものは、すなはち国家
を覆
すの利
き器
たり、人民
を絶つの鋒
き剣
なり。また佞
み媚
ぶるものは、上
に対
ひてはすなはち好みて下
の過
りを説き、下に逢ひてはすなはち上の失
ちを誹謗
る。それこれらのごとき人、みな君に忠
しさなく、民
に仁
みなし。これ大いなる乱れの本なり。
悪を懲らしめ善を勧めることは、古くからの良い決まりである。
そのため、人の善を隠さず、悪を見たら必ず正せ。
もしへつらい欺く者がいれば、それは国家を覆す道具であり、人民を傷つける剣となる。
また、おべっか使いは、上の前では下の過ちを語り、下の前では上の失敗を非難する。
このような人々は、君主に対して忠誠心がなく、民に対して思いやりもない。
これは大きな混乱の元となる。
第7条
七にいはく、人おのおの任
しあり、掌
ることよく濫
れざるべし。それ賢哲
官
に任
すときは頌
むる音
すなはち起る、奸
しきひと官を有
つときは禍
ひ乱れすなはち繁
し。世に生れながら知る人少なし、よく念
ふときに聖
となる。事、大いなり少
けきことなく、人を得てかならず治まる。時、急
き緩
きことなく賢
に遇
ふ、おのづからに寛
るかなり。これによりて国家
永久
にして、社稷
危
ふからず。故
古
の聖の王
は、官のためにもつて人を求めて、人のために官を求めたまはず。
各人には担当する仕事がある。
むやみに他の職務に干渉してはならない。
賢者が任命されれば称賛の声が上がり、
よこしまな者が職につけば災いと混乱が増える。
生まれながらにして物知りな者は少ないが、よく考えて正しい判断ができるようになる。
どんな事でも、適任者を得れば必ず上手くいく。
緊急か否かに関わらず、賢者に任せれば自然と余裕が生まれる。
これによって国家は永続し、社会の基盤も揺らぐことはない。
だから古の聖王は職のために人を求め、人のために職を求めなかった。
第8条
八にいはく、群卿
・百寮
、はやく朝
りておそく退
づ。公
の事
なし。終日
に尽しがたし。ここをもつておそく朝るときは急
やけきに逮
ばず、はやく退づるときはかならず事
尽きず。
高官たちよ、早く出勤し遅く退出せよ。
公務は休む暇もなく、一日中でも処理しきれない。
そのため遅く出勤すれば緊急の事態に間に合わず、早く退出すれば必ず仕事が残る。
第9条
九にいはく、信
はこれ義
の本なり。事
ごとに信あるべし。それ善
さ悪
しき、成り敗
らぬこと、かならず信にあり。群臣
ともに信あらば、なにの事か成らざらん。群臣信なくは、万
の事ことごとくに敗れなん。
信義は正義の基本である。
あらゆる事に信義があれば、善悪の成否は信義にかかっている。
君主と臣下の間に信義があれば、成し遂げられないことはない。
第10条
十にいはく、忿
を絶ち瞋
を棄てて、人の違
ふを怒らざれ。人みな心あり、心おのおの執
ることあり。かれ是
んずればすなはちわれは非
んず、われ是みすればすなはちかれは非んず、われかならず聖
なるにあらず、かれかならず愚かなるにあらず、ともにこれ凡夫
ならくのみ。是く非しきの理
、たれかよく定むべき。あひともに賢く愚かなること、鐶
の端
なきがごとし。ここをもつてかれの人瞋
るといへども、還
りてわが失
ちを恐れよ。われ独り得たりといへども、衆
に従ひて同じく挙
へ。
怒りを抑え、人が自分に逆らうことに腹を立てるな。
人にはそれぞれ考えがある。
相手が正しければ自分が間違っており、自分が正しければ相手が間違っている。
自分が必ずしも聖人でなく、相手が必ずしも愚か者ではない。
共に凡人である。
是非の道理は、誰が正確に定められようか。
賢さと愚かさは、輪のように始めも終わりもない。
そのため相手が怒っても、かえって自分の過ちを恐れよ。
たとえ自分が正しいと思っても、多数に従って行動せよ。
第11条
十一にいはく、あきらかに功
み・過
りを察
て、賞
し罰
ふることかならず当てよ。日ごろ、賞すれば功みに在
いてせず、罰へば罪に在いてせず。事
を執
れる群卿
、よく賞・罰へをあきらかにすべし。
功績と過ちを明確に見極め、賞罰を適切に行え。
最近は、功績に対する褒賞も、罪に対する処罰も適切でない。
事を執り行う高官たちは、賞罰を明確にすべきである。
第12条
十二にいはく、国司
、国造
、百姓
に斂
らざれ。国にふたりの君あらず。民
にふたつの主
なし。率土
の兆民
は王
をもつて主とす。所任
せる官司
はみなこれ王の臣
なり。いかにぞあへて公
と、百姓に賦斂
らん。
国司・国造よ、勝手に民から税を取るな。
国に二人の君主はなく、民に二人の主人はいない。
全国民は天皇は主として仰ぐ。
任命された役人はみな天皇の臣下である。
どうして公と共に民から勝手に税を取ることができようか。
第13条
十三にいはく、もろもろの官者
に任
せるは、同じく職掌
を知れ。あるいは病し、あるいは使ひありきとて事
に闕
ることあり。しかれども知ること得んの日には、和
ふことむかしより識るがごとくにせよ。それあづかり聞くことなしといふをもつて、公
の務
をな防
ぎそ。
すべての役人は、それぞれの職務内容を理解せよ。
病気や出張で仕事を怠ることがあっても、
職務に戻った日には以前から知っていたかのように調和して仕事をせよ。
自分の担当外だからといって、公務の妨げになってはならない。
第14条
十四にいはく、群臣
・百寮
、嫉
み妬
むことあることなかれ。われすでに人を嫉
むときは人またわれを嫉む、嫉み妬む患
へその極
まりを知らず。このゆゑに智
おのれに勝
るときはすなはち悦
びず、才
おのれに優
れるときはすなはち嫉妬
む。ここをもつて、五百
にて後
いまし今賢
に遇
ふとも、千載
にてももつてひとりの聖
を待つこと難し。それ賢
しき人・聖を得ずは、なにをもつてか国を治めん。
高官たちよ、互いに妬み嫉むことがあってはならない。
自分が人を妬めば、人も自分を妬む。
嫉妬の害に限りはない。
そのため、知恵が自分より優れていれば喜ばず、才能が自分より優れていれば妬む。
そういうわけで500年に一度賢者に出会えるとしても、1000年経っても聖人に出会うことは難しい。
聖人や賢者を得られなければ、どうやって国を治められようか。
第15条
十五にいはく、私
を背きて公
に向
くは、これ臣
の道なり。すべて人私あるときはかならず恨みあり、憾
みあるときはかならず同
ほらず、同ほらざるときはすなはち私をもつても公を妨
ぐ。憾み起るときは、すなはち制
に違
ひ法
を害
る。故
初めの章
にいはく、上
下
和
ひ諧
ほれといへるは、それまたこの情
なるかな。
私利私欲を捨てて公のために尽くすのが、臣下の道である。
人々に私心があれば必ず恨みが生まれ、恨みがあれば必ず調和が乱れる。
調和が乱れれば私利私欲が公務の妨げとなり、恨みが起これば道理に反して法を破ることになる。
だから第一条で述べたように、上下の調和が大切なのだ。
これもまたその心なのだろう。
第16条
十六にいはく、民
を使ふに時をもつてするは、古
の良き典
なり。故
に冬の月に間
あり、もつて民を使ふべし。春より秋に至るまでにて農
桑
の節
なり、民
を使ふべからず。それ農せずはなにをか食
はん、桑
らずはなにをか服
ん。
民を労働させる時期を考えることは、古くからの良い決まりである。
冬の間は農閑期なので、民を使っても良い。
春から秋は農作業の時期なので、民を使ってはならない。
農業をしなければ何を食べるのか。
養蚕をしなければ何を着るのか。
第17条
十七にいはく、それ事、独り断
むべからず、かならず衆
とよく論
ふべし。少
けき事
はこれ軽
しく、かならずしも衆とすべからず。ただ大いなる事を論ふに逮
んでは、もしは失
りあること疑はしきときあり、故に衆とあひ弁
ふるときは辞
すなはち理
を得
。
物事は独断で決めてはならない。
必ず皆で議論すべきである。
小さな事は重要でないので、必ずしも皆で議論する必要はない。
ただし重要な事を議論する時は、間違いがあることを懸念せよ。
そのため皆で議論して判断する時は、物事は道理にかなったものとなる。
まとめ
十七条憲法は、制定から1000年以上が経過していますが、それでもなお、私たちが胸に刻むべき教訓が多く含まれています。
何かにつまづいたり、うまくいかないことがあって悩んでいる時は、十七条憲法を読んでみてください。
もしかすると解決のヒントが眠っているかもしれません。
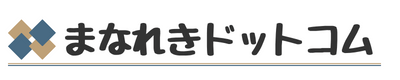

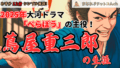
コメント
とてもわかりやすく面白く、勉強させていただいております。
ただ第12条の解説は、孫請け構造が悪いことのように書かれていますが、これには違和感を持ちました。現代の下請け・孫請けは組織におけるピラミッド構造にすぎず、それ自体が悪いわけではないと思います(階層が多すぎるとコスト高になる弊害はありますが、これも組織内の階層と同じことです)。むしろ現代で第12条に近い話は、たとえばリベートを担当者や部署が懐に入れるような行為や、税や保険で官僚機構が無駄に肥大するようなケースなどかなと思います。
第13条の「丸投げは駄目」というのも少し違和感があります。それより「仕事の内容や現場を知る努力をせずに勝手な命令をするな」といったところではないでしょうか。
余計なお世話でしたらすみません。
今後も楽しませていただきます。