

今回は、弥生時代の日本について書かれた貴重な史料の1つ『後漢書』東夷伝についてわかりやすく丁寧に解説していくね!
youtube解説もしています。読むのが面倒な人は動画がオススメ◎
『後漢書』東夷伝とは?

後漢書は、5世紀の中国(当時の王朝は宋)だった頃、范曄という人物が書いた歴史書です。
後漢書のうち、東夷伝という巻に紀元100年前後の日本の様子が書き残されていました。
後漢書の中の東夷伝の巻という意味で、『後漢書』東夷伝というカッコを使った表記になっています。
『後漢書』東夷伝の内容は?

まずは、『後漢書』東夷伝の日本に関する記録の原文を載せておきます。すぐ後に現代語訳も載せてるので、内容は分からなくてもOKです!
【原文】
建武中元二年(57年)、倭の奴国、貢を奉じて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。
安帝の永初元年(107年)倭の国王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う。
桓霊の間(147〜189年)、倭国大いに乱れ、更相攻伐して歴年主なし。
現代語訳するとこんな感じ。
【現代語訳】
紀元57年、倭の奴国が、貢物を持って漢へやってきた。使者は自らを大夫と称した。奴国は倭の南方に位置し、光武帝は奴国に官職を与えるための印鑑を授けた。
107年、倭の国王である帥升たちが、奴隷(※)160人を献上して、安帝と会うことを願い出た。
霊帝の在位期間(西暦100年代後半)、倭国は大いに乱れ、代わる代わる互いに攻め合い、長い間、国を統一する者がいなかった。
※原文にある「生口」は奴隷のことだと考えられていますが、解釈には諸説があります。(この記事では奴隷ってことにしています。)
これらの内容について、高校レベルで大事なところをピックアップして紹介していきます。
金印の発見
1つ目のポイントは、
光武賜うに印綬を以てす。(光武帝は使者に奴国に官職を与えるための印鑑を授けた。)
ってところです。
1784年(江戸時代)、福岡県の志賀島で「漢委奴国王」って書かれた金の印鑑(金印)が土の中から発見されました。

「漢委奴国王」は、そのまま「漢の倭の奴の王」ということを意味しています。
この金印は、『後漢書』東夷伝に記録されている奴国が漢からもらった印鑑のことだと考えられていて、『後漢書』東夷伝の内容を物的証拠で確認することができています。

『後漢書』東夷伝では、「奴国は倭国の南の方にある!」って書かれていますが、金印が見つかった福岡県あたりにあった・・・という説が現在の主流になっているよ。
国王「帥升」は何者?
もう1つのポイントは、
安帝の永初元年(107年)倭の国王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う。(107年、倭の国王である帥升たちが、奴隷160人を献上して、安帝と会うことを願い出た。)
の部分です。
ここで登場する倭国王の帥升っていうのが何者なのか、実はよくわかっていません。
帥升のことを面土国の王と書いてある歴史書もあるので、奴国とは別の小国の王・・・と考える説もあれば、
「いやいや!倭国王っていうぐらいだからきっと小国たちを束ねていた王の中の王だったに違いない!」という説もあります。
いずれの説でも、九州にいた人であること間違いないだろう・・・と言われています。
さらに、帥升は奴隷160人を連れてきたとあり、弥生時代には奴隷のような身分があったことも察することができます。
弥生時代は、環濠集落や高地性集落などの防御力を高めた集落がたくさんあり、争いが絶えなかったことを示しています。
奴隷というのも、もしかしたら、争いの勝者が敗者たちのことを奴隷として扱い、漢に献上したのかもしれません。(繰り返しになりますが、生口の解釈には諸説あります。)
奴国はなぜ後漢に使者を送ったのか
ところで、奴国はなぜ後漢に使者を送ったのでしょうか。
海を渡ってアジア大陸に渡るというのは、難破・遭難リスクもある命がけの行為です。命をかけてまで後漢に訪れる価値はあるのでしょうか。
この話は『漢書』地理志の記事でもしていますが、改めて解説しておきます。
実は、奴国にとって後漢に訪れることには大きく2つのメリットがあったと考えられています。
後漢の後ろ盾を得て、倭国内の争いでマウントを取ろうとした。
中国(当時の王朝は後漢)の最新の文明・技術を手に入れて、他国よりも有利な立場に立とうとした。
このうち一番の理由は、先ほど登場した金印の話と密接に関係しています。
奴国は、後漢の光武帝から「倭の奴の国王」であることを認められ、その証明として金印を授かっています。
この金印は、小国同士の争いでめちゃくちゃ有効利用できました。

おいおい君、俺の国に攻め込んじゃっていいのか?
俺は光武帝から金印を授かっているんだぞ。俺が負ければ、後漢も黙ってないと思うけど、そんな俺のこと攻めちゃっていいのかな?^^
と、他の国に対してマウントをとることができたのです。
金印は持っているだけで、他国から攻め込まれにくくなるし、王としての威厳も高まるので、リスクを冒してまで海を渡って漢に行く価値は十分にあったわけです。
倭国騒乱、卑弥呼登場へ
最後3つ目のポイントは、
桓霊の間(西暦100年代後半)、倭国大いに乱れ、更相攻伐して歴年主なし。(霊帝の在位期間(147〜189年)、倭国は大いに乱れ、代わる代わる互いに攻め合い、長い間、国を統一する者がいなかった。)
の部分です。
奴国みたいな金印をゲットしてイケイケな国が現れても、争いが収まることはありませんでした。100年代後半に入ると、むしろ争いが激しくなって、『後漢書』東夷伝にあるように倭国は大いに乱れました。
『後漢書』東夷伝に書かれているのはここまで。この大乱の結果までは書かれていません。
この大乱の結果は、もう1つの重要な歴史書『魏志』倭人伝に書かれています。
200年頃、この騒乱を終わらせた1人の女性が登場します。
・・・その女性の名は卑弥呼。
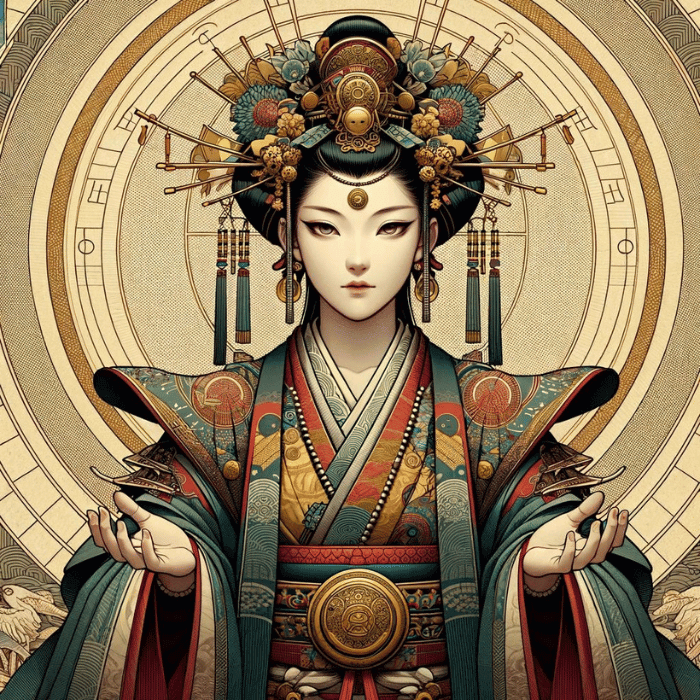
卑弥呼は、○○の能力で殺し合いをしていた国々をまとめ上げ、自らも邪馬台国という国の女王として君臨し、日本に平和をもたらしてくれました。
・・・、とここから先は『魏志』倭人伝の話になるので、続きは『魏志』倭人伝の記事を読んでみてください!
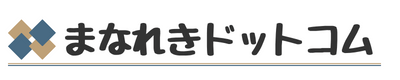
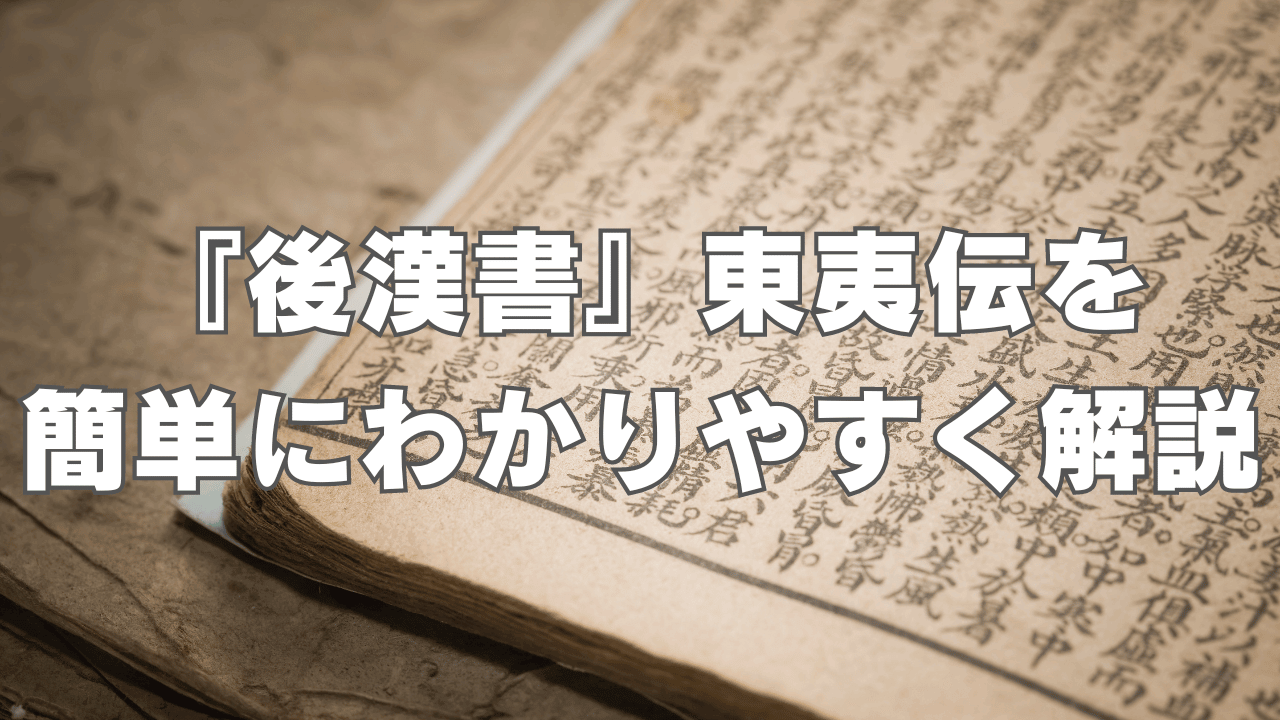
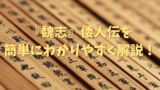
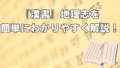

コメント
後漢書より考えても、古事記を正しく理解すれば、神武天皇の即位はどう考えても西暦250年頃となりそうです。
狗奴国の男王、卑弥弓呼を崇神天皇とすれば、スッキリ説明が出来ます。